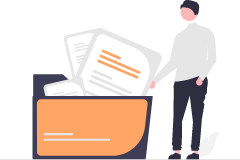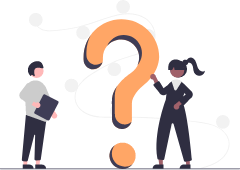特集・お役立ち 英語研修が成功している企業は何が違うのか ~成功基準~
英語研修を導入いただく企業様は年々増え続けていますが、研修内容に満足しながら継続している場合もあれば、新規導入を検討中、または過去に実施はしていたが風化してしまったなど、状況は様々ではないでしょうか。
それでは「成功する英語研修」と「失敗する英語研修」は何が異なり、何を以って研修は成功と言えるのでしょうか。
英語研修を成功させるカギのひとつは
です。
それでは詳しく見ていきましょう。
英語研修を導入する目的は企業様ごと、その時々の状況によって大きく異なってきます。
スピーキング力を伸ばしたい、プレゼンテーション対策、電話応対、新入社員研修、クレーム対応、昇格要件、海外取引先との対応、海外赴任、福利厚生の一環・・・など、目的は無数に存在しますが、
その目的が決まったら、次は「到達目標」を明確にします。
例えば、研修の目的が海外からの自社商品への問合せに対する「電話応対」だと仮定します。
この目的に対しての到達目標は、「誰」が「何が出来るようにする」かによって研修内容が異なりますね。
到達目標は?
到達目標によって、研修に必要とされる時間や費用などは大きく異なりますが、その到達目標を達成するために、どのような研修が必要とされるのかを逆算して、社員様の現状の英語レベル、ご予算、目標達成期限などに応じて研修をカスタマイズしていくのです。
まずはこちらをチェック
そして次は研修の方向性(ベクトル)のお話です。
研修実施にあたり対象となるのが下記4つのグループです。このグループの皆が同じベクトルを向いていなければ研修が失敗する可能性が高くなる、
それでは同じベクトルを向くとはどういう事なのでしょうか。
4つのグループ
-
会社(または上層部)
-
ご担当者様(以下「ご担当」)
-
受講者様(以下「社員」)
-
研修業者(以下「業者」
例えば
-
会社「海外からの商品問い合わせが増えているから英語研修を始めよう。社員が英語で取引先とコミュニケーションがとれるよう、しっかりとした厳しい、成果の出る研修を実施するように。全額会社負担で実施する方針だ。」
-
ご担当「会社負担で研修をするからには、成果を出さなければ。ただ、英語嫌いな社員が多いから、厳しくし過ぎると英語学習から逃げてしまうのでは?他の研修に比べて英語に対して苦手意識が高い社員が多いのは事実だ。」
-
業者「英語での商品説明には想定外の質疑応答も多い為、リスニング、スピーキング共にかなりのレベルアップが必要とされる。成果のしっかり出る厳しめの研修プログラムをご希望とのことなので、1日最低2時間は学習して頂く必要がある。受講者様の学習負担は大きくなるが、話せるようになってご満足頂ける研修にしなければ。」
-
社員「英語は苦手だし現在の業務量を抱えながら勉強する時間は捻出できない。毎日残業もあるのにいつ勉強したら良いのか。他の社員の前で間違えたら恥ずかしい。」
上記例は少しおおまかなセッティングで、実際には皆さま研修前にはもっとしっかりと検討をされますし、我々研修業者も事前に問題点や課題をご提示させていただく為、大きな問題に至る事は少ないのが事実です。
ただし、このように4つのグループに大きくズレが生じているケースは実は少なくはありません。
研修業者が事前に各グループのヒアリングをしっかり行う事で、各グループの意向を正確にくみ取ったうえでズレを解消し、皆のベクトル(意向)をしっかり同じ方向へ揃えます。

その為に各グループがすべきことはこちら
会社
ご担当者様
上層部のご意向を理解し、また、社員様に近いところにいる橋渡し役としての潤滑油的存在として、研修業者と進捗状況や課題点を常に共有して頂ける縁の下の力持ち存在。
研修実施に関して社員様の現状(英語学習に対する意欲や現状の仕事量など)を研修業者にお伝え下さい。
受講者様
英語が苦手な方にとっては、業務命令とはいえ英語学習は苦痛でしかないと思っている社員様は少なくない。もちろん、「英語を学びたいと思っていたけど自分では機会がなかった!」と、英語研修に参加出来てとても嬉しく思って頂ける社員様がいることも事実。
苦手な方にとっては、英語を学習しようと思う自ら思わせるモチベーション作りと不安を取り除く方法、モチベーションの維持、間違えたら恥ずかしい事などへの対策が必要。英語学習を楽しいと思って頂けたらまずは研修成功に向けての第一歩に繋がる。
研修業者
研修成功の為に皆様からしっかりとヒアリングをし、どのような研修内容で目標を達成するのか、その為に必要とされる事などをご提案。
過去の様々な研修事例を熟知した研修アドバイザーだからこそ、皆様に心地よく学習頂ける方法をお伝えできる存在。
色々とお伝えしてきましたが、最後に、何を以って研修は成功と言えるのでしょうか。
答えは
研修に関してのご相談は以下お問合せフォームにて随時受け付けております。
現在研修実施中の方、新規でご検討の方、どなた様でもお気軽にお問合せ頂けますと幸いです。
研修運営に携わる方におすすめ 法人向け 英語研修総合パンフレット
創業50年を迎えるイーオンが企業や学校教育機関向けにて提供する英語研修サービスの総合案内パンフレットです。
優秀な教師陣や独自のカリキュラムなどの、イーオンの強みを活かした最適なプログラムをご提案します。
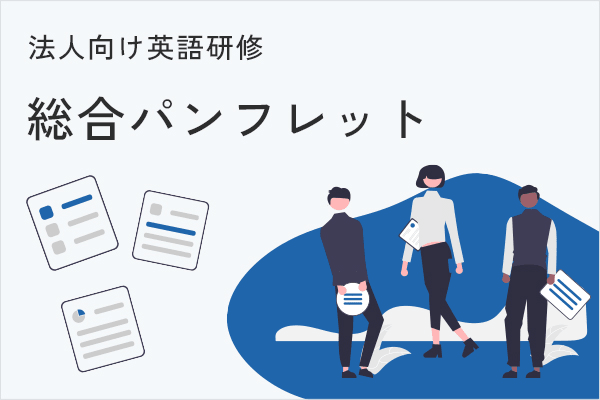
編集者
長年培ってきた研修ノウハウを企業の課題、目的に沿ってご紹介。
ビジネスをグローバルに加速させる最高の英語体験を提供すべく、価値あるメディアを目指します。
研修に関してのご相談は以下お問合せフォームにて随時受け付けております。